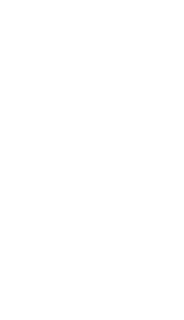お葬式の後、すべての事が終わると、皆さんに出す食事のことを「精進明け」といいます。これは、亡くなられた人のことを思い、お葬式が済むまでは、生臭い物は一切口にせず、仏さまがお説きになられた不殺生の戒めを守ろうという仏教徒の生活習慣によるものです。
日頃、美味しい物を何の考えもなく食べている現代人にとっては、命という問題を、身をもって考えるいい機会だと思っています。ところが、今の時代は、この精進明けを「精進あげ」という人が多いのです。精進明けとは、精進潔斎をする期間が明けたという意味です。精進あげと濁っていえば、野菜の天ぷらのことです。もっとも、天ぷらというのは、正しくは、魚や貝を油で揚げたもので、江戸時代に日本に入って来た西洋料理なのだとか。その語源はポルトガル語かスペイン語だろうといわれていますが、精進揚げという場合には、その衣にする小麦粉には卵を入れないのが正式なのだそうです。
話が横にそれました。精進明けの料理を口にした人々の顔をみると、どの顔にも、どこかほっとしたような表情が感じられます。それは、今までの緊張からやっと開放されたという思いもあるのでしょうが、それは人間としてはごく自然な感情といえるのではないでしょうか。
ところで、懐石料理という言葉を耳にしたことがあると思います。石を懐に抱くと書きますが、これも仏教から来た言葉です。昔は、修行するお坊さんたちの食事は午前中1回と決められていました。それではお腹もすくし、寒さにも耐えられないというので、懐に温石(おんじゃく)という温めた石を抱いて、じっと辛抱したのが懐石料理という言葉の起こりです。やがて時代と共に、それならば、軽い食事をすることくらいは認めようというので、懐石料理というのができたのだとか。いわば、一汁三菜の簡単な精進料理が懐石料理なのです。
ところが江戸時代になると、これも、人が集まり会する飲み食いの宴会のご馳走を、会席料理というようになりました。「かいせき」という音は同じなのですが、中味はまったく反対です。やはりご馳走をお腹いっぱい食べたいというのが、人の本音なのでしょうか。
油を使った精進料理の中に、同じく江戸時代に入って来た普茶料理がありますが、この中には、大豆を使いながらも、牛肉とまるで同じような味を味わえる逸品もあるのです。
仏さまの戒めがあればこそ、凡夫の私たちは工夫するのでしょう。それもまた、暮らしの中の仏の教えなのかもしれませんね。