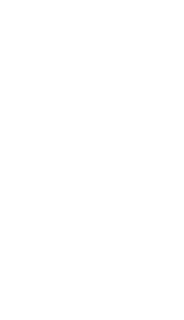私たちは、仏さまの教えを信じることを、「帰依」と表現したり、「帰命」といったりします。「帰依」とは、依り所とするという意味、「帰命」とは、命をささげるという意味でしょうか。
いずれも、仏さまの教えを絶対に信じますという心の表れなのでしょうが、私はこの言葉に、「帰る」という字が使われていることに、とても興味を憶えます。
それは、人生も70の年を重ねると、先が見えたような気になり、その終着駅、すなわちゴールは何処にあるのだろうと考えたりするからかもしれません。そんな時、2009年に101歳で亡くなられた松原泰道老師が著された「楽しく生きる仏教」という本の中で、とても身に沁みる言葉に出会いました。
泰道老師は、若い頃より、人々に仏さまの教えを分かりやすく伝えたいと願って、ナームの会の会長を引き受けられ、活躍された臨済宗のお坊さんです。
その老師が、この本の中で、冒頭に、「ナームは、ほとけの家に帰り、身も心も安らぐ、よろこびの声だ。『お帰りなさい』と『ただいま』の親子の同時発言だ。ナームは、ほとけを仰ぎ、人を信ずる、いのちといのちが呼び合う言葉だ」と書かれています。
ナームという言葉は、インドの言葉を音訳したもので、それが、帰依とか帰命を意味する言葉であることは、私も知っていました。それを生活の中で口にする、「ただいま」と「お帰りなさい」という言葉に表した老師の解説に、思わず、ウーンと唸ってしまいました。
子どもが、「ただいま」といってドアを開けたとしても、親は仕事に出かけ、「お帰りなさい」という声を聞くことが少ない現代ではないでしょうか。これでは、親子の温かい関係も育たないし、宗教心が失われていくもの当然な事だと考えさせられました。
このナームの心を説明するために、泰道老師は、五十九歳でこの世を去った詩人、高見順さんのその年に発表したこんな詩を紹介しています。「帰れるから、旅は楽しいのであり、旅の寂しさを楽しめるのも、我が家にいつかは戻れるからである」というこの詩の中に、私たちが求めてやまない絶対なる安らぎの世界を教えられる気がしました。
ゴールまで、私もどれほどの人生が残されているかは分かりません。でも、100歳という年を迎えるまで、人生を前向きに生きられた老師を思えば、あなたも元気がでるのではないでしょうか。
帰る所があればこそ、お互い、今日一日にナームしたいものですね。