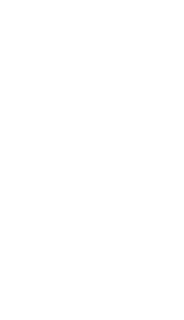動脈硬化や高血圧、それに心筋梗塞や糖尿病など、中年以降の人に多くみられる病気のことを、成人病といいます。ところが、最近、耳慣れない病名を聞いたのです。それは「生活習慣病」。
「いったい、どんな病気なんですか」と知り合いのお医者さんに尋ねると、「昔の成人病です。今では、子どもたちにも、そんな病気が多くなっているので、呼び名を変えざるを得なくなったんですよ」との答えが返って来ました。飽食の時代といわれるこの時代、今までは考えられなかったような病気が子どもたちの健康をむしばもうとしているのです。まさに、その呼び名のとおり、生活習慣の違いによって起こっている病気なのでしょう。
実は、私がこの事に興味を持ったのは、「言葉のクスリ、毎朝一話、出勤前に読む本」という本に出ていた、「人間の内臓は5000年前のまま」という話を目にしたからです。
著者の太田典生さんは、医者であり作家でもある渡辺淳一さんの「成人病の原因は、人間の内臓が5000年前のままなのに、食生活だけが変わってしまったことにある」という言葉を紹介しながら、贅沢に慣れてしまった現代人の生活習慣に警告を発しています。
5000年前の私たちの先祖は、野や山を駆けめぐり、川や海に出て、自然の中から食材を求めていました。何も収穫のなかった時には、飢えをしのがなければならないようなこともあったでしょう。
ところが、そのような環境で生き抜いた先祖と同じ内臓を持ちながら、私たちが体を使わず、ただ美味しい物を食べる生活を繰り返している。これでは自殺行為に等しいと太田さんはいうのです。
5000年前の先祖の内臓と同じなら、私たちの体は粗食にも十分耐えられるように造られているはずです。そこに必要以上のエネルギーが貯まれば、身体にいろんな故障が出て来るのは、ごく当たり前のことではないでしょうか。そう思いながら私は、これは身体だけではなく、心の問題も同じではないかと考えました。
近頃の子どもたちには、子どもらしさがない。まるで年寄りのように無気力な子どもが多くなったともいわれています。それを子どもたちのせいにするつもりはありませんが、これもまた生活習慣病といえるのではないでしょうか。
お釈迦さまは、自分を律することから悟りへの道は開かれるとお説きになっています。それならば、5000年前の先祖を心に思い浮かべることも必要な時代ではないでしょうか。
「時には、お医者さんの指導のもと、3日間の断食を試みています」という太田さん。「そんな時、心にすがすがしさが戻って来ます」という言葉がなんとも印象的だったのです。
心も生活習慣病