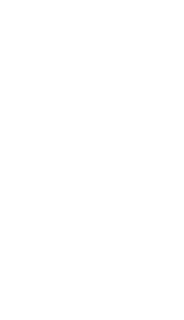永い眠りと書いて、「えいみん」と読みます。それが人の死を意味する言葉だということは、どなたもご承知のことと思います。
私たちお坊さんが枕経にお伺いして、なにはともあれ、拝見させていただくのは、亡くなられた方のお顔です。息を引き取られた後の安らかなお顔に接すれば、まずはホッとします。「ご病気で、苦しまれたかもしれませんけど、安らかに次の世に旅立たれたご様子で、よかったですね」と申し上げると、ご家族も一同に肯いて下さいます。もちろん、そうでないお顔に接することもないではありません。そんな時には、「大丈夫ですよ。お経をあげ、お題目をお唱えすれば、きっと安らかなお顔になられますから」とお話しすることにしています。それは、なんのこだわりもなくこの世に別れを告げて欲しいという願いがこちらにあるからです。
私は、今、「別れを告げる」という言葉を口にしました。その別れを告げるという言葉を、ちょっと難しくいえば、告別となります。死んだ人も、それを見送るこの世に残っている人も、これが最後の別れだというのが告別式、分かりやすくいえば、お別れの式です。しかし、お葬式というのは、単なるお別れの儀式であってはなりません。なぜなら、お葬式というのは、私たち仏教徒の場合、別れるのは悲しいけれど、その悲しみを乗り越えて、亡き人に次の世をしっかりと生きて下さいという願いを託す儀式だからです。
それならば、亡き人にいつまでも眠ったままの状態でいてもらっては、困るのではありませんか。なんといっても、この世を去ったその日から、次の世の居場所がきまるまでの七、七、四十九日の間、中陰といって、亡くなられた方は、誰もいない暗闇の道を1人で歩かなければならないと説かれているからです。
実は「永眠」という言葉は、キリスト教文化が伝わって来るまで、私たち日本人の死後の世界観にはなかった言葉だということを最近知りました。その学説によれば、キリスト教では、神様の裁きがあるまでは、亡くなった人に対し、お墓の中で静かに眠っていて下さいと願うことが、永眠という本当の意味なのだそうです。
それならばと、私は考えました。仏さまを意味するインドの言葉、ブッダには、「目覚める」という意味があるからです。眠ったままでいてはならない、一時も早く目覚めようというのが、仏さまの願いだといっていいでしょう。
私たちが、亡き人へ手を合わせ、手向ける祈りは、眠りの後の爽やかな目覚め、そして、明るい未来への旅立ちを願うこと。それがお葬式の本当の意味だとあなたにも知ってもらいたいのです。